乗入れ構台・荷受け構台に関する問題は、建築施工管理技士試験だけでなく、建築士試験でも頻出します。
仮設構造物に関する基礎知識としても重要で、施工計画や現場管理を行う技術者にとっては避けて通れないテーマです。
本記事では、過去問にもとづいた頻出ポイントと注意すべき規定をわかりやすく解説します!📚✨

乗入れ構台に関する規定
乗入れ構台は、重機や資材運搬車両を構内へ安全に乗り入れさせるための仮設構造物です。
以下の点が試験で問われやすいポイントです。
支柱
支柱に関しては、以下の2つが要点です。
- 支柱は建物の構造体(基礎、柱、梁、耐力壁)を避けて設置しなければなりません。
支柱間の感覚はおおむね5mごとが目安です。 - 支柱と山留め工事の切梁支柱については、荷重に対する安全性が確認できれば兼用可能です。
💡頻出ポイント:「使用する施工機械や車両の配置によって決める」=×です!
構台
構台の大引下端は、下にある床スラブの上端より20~30cm程度上方に設定します。
躯体コンクリートを下部に打設する時に、床スラブの均し作業をするクリアランスを設るためです。
💡頻出ポイント:「10cm程度」=×です!
車両の乗り込み
構台幅は、以下の通り用途や車両の通行方式によって必要幅を計画する必要があります。
- 道路から乗入れ構台までのスロープ勾配:1/10~1/6程度
- 交互一方通行の1車線用:4m以上
- 対面通行の2車線用:6m以上
- クラムシェル(バケットを上下させて掘削する重機)を用いる場合は旋回半径を考慮して8m以上
✅チェック:車幅に対する尤度と、機械の作業スペースを考慮しましょう!
荷受け構台に関する規定
荷受け構台は、トラックやクレーンから資材を受け渡すための仮設構造物です。
荷重に関する規定がポイントになります。
作業荷重の計算方法
作業荷重は、構台の自重+積載荷重の合計の10%増しで見積もります。
💡頻出ポイント:自重と積載荷重の合計の「5%」とした=×です!
荷重の偏り
荷重のかかり方は、構台スパン全体の60%範囲に荷重が集中すると仮定して設計します。
✅チェック:現実の荷下ろし作業では、荷を1ヵ所にまとめて仮置きするなど荷重が偏るためです!
おすすめ資料
ヒロセホールディングス株式会社の公式YouTubeチャンネルで
乗入れ構台の施工過程が、3Dモデルでビジュアル的に分かり易くまとまっています。
(参考:ヒロセホールディングス株式会社 乗入れ構台架設ステップ動画)
まとめ
乗入れ構台・荷受け構台は、仮設計画の要となる設備です。
設計・施工段階での安全確保はもちろん、施工管理技士試験でも細かい規定が問われますので
出題傾向を把握しておくことが合格への近道です!🏗️💪
これらの知識は、建築施工管理技士試験だけでなく、
建築士試験や実際の設計業務でも活用できる重要なポイントです。
基本的な考え方を身につけて、試験では確実に得点しましょう!
👇建築施工管理技士の試験勉強におススメの参考書です👇
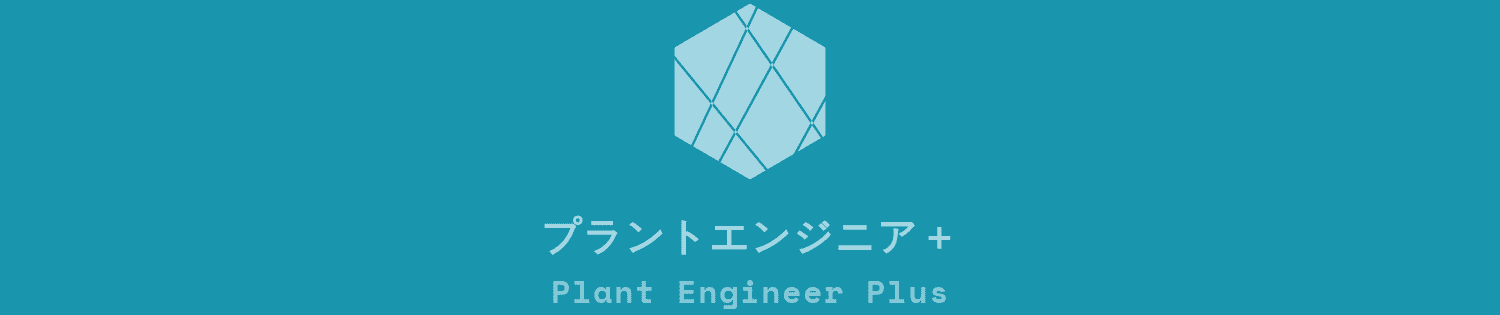




コメント